
お茶づくりのこだわり
Our commitment to tea making
お茶の栽培について

「肥料の話」
植物性・動物性の有機質肥料を施します。化学肥料は使用しておりません。施肥量は窒素量で慣行栽培の半分以下となります。慣行栽培に比べ収量・生育が劣りますが、すっきりとした飲み口の釜炒り茶・品質の優れた和紅茶を作る上で必要な量だけを施すという考えです。
また茶園周辺の草木を刈り、茶の木の株元に投入したり、落ち葉を集めて幼木園に敷いたりしています。草払いをした草や剪定した茶の葉や枝もそのまま土に還ります。肥料に頼りすぎないことで、茶葉本来の味・品種の特性を導きやすくなると思っています。

「茶の木の話」
茶の木は年に3回から4回ほど機械で剪定を行います。
(乗用の機械はありません・・・)
茶園の場所、樹齢、そして品種によっても生育は大きく異なります。また病害が入ってしまう茶畑もあります。状況を見ながら浅めに整える剪定をしたり、深く刈り入れたり、時には葉の層が無くなるところまで刈り落とし回復を待ちます。古くなって回復が望めなくなった茶園は改植をします。収穫までは5年ほどかかりますが、新しい品種を植えるのには良い機会です。また、在来種という何十年も前から育ててきた茶園も大切にしています。現在たくさんの品種を少しずつ栽培してラインナップを増やしていますが、在来種の茶葉にはその土地で根づき、育ったオリジナルの素晴らしさがあります。

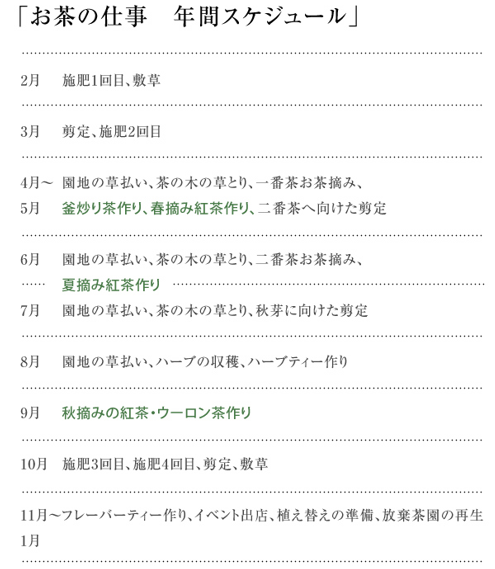
お茶づくりの話
「釜炒り茶」
すっきりとした飲み口でお茶本来の味を感じることのできる釜炒り茶。
飲み疲れせず、すっと身体に馴染む釜炒り茶を目指します。
お茶のカジハラでは、4月から5月の時期に一番茶で釜炒り茶という緑茶を作ります。釜炒り茶は現在主流な蒸し製の緑茶とは製法が異なります。摘み取った生葉を300℃にもなる直火の釜で炒り、酸化酵素の働きを止め緑茶にします。また、精揉(せいじゅう)と呼ばれる、茶葉を伸ばす工程が無いため形状はぐりっとした勾玉状になります。釜香と呼ばれるすっきりとした味わい、澄んだ薄黄色の水色が特徴です。
当園の工場では数年前に機械の入れ替えを行いました。しかし、第一工程の生葉に熱を加え殺青(さっせい:葉の酸化酵素の動きを止める)する「炒り葉機」、仕上げの締め炒りという作業で使っている丸窯はそのまま残しました。どちらも昭和初期から受け継がれてきた器械です。
伝統を守りながらも研究を重ね、質の高いおいしい釜炒り茶を追及しています。ここ数年は収穫できる品種が増えたことから単一品種で作るシングルオリジンティーにも力を入れております。
「和紅茶」
品種ごと季節ごとに茶葉の香りや味わいを最大限に引き出して、
品質にこだわった和紅茶を目指します。
和紅茶は日本で育った茶葉を使い、日本で紅茶に加工されたものです。現在日本各地で特色のある和紅茶が作られています。渋みが少なくまろやかな味わいで、ストレートで飲めるのが基本的な特徴です。品種や発酵度合いの違いでも幅広い味わいが楽しめます。
当園でも品種、茶摘みの季節ごとにロットを分けて販売しております。例えば「べにふうき」という品種で作る紅茶には、春積み(ファーストフラッシュ)、夏摘み(セカンドフラッシュ)、秋摘み(オータムナル)があり、それぞれ特徴が異なります。品種や季節、製茶時の気温や湿度によって萎凋(いちょう:生葉を萎れさせる重要な工程)やその後の揉捻(じゅうねん:茶葉を揉む工程)、そして発酵の時間を変えていきます。品種や状況に合わせて製茶するのは手間がかかりますが、茶葉の特徴・特性を引き出すため工程には妥協しません。また品種によっては雑味を出さないように茶葉を切断せずにホール(フルリーフ)の形状で販売します。手選別になるため手間はかかりますが、これも茶葉本来の味を引き出すためです。

